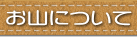|
西黒森は、四国の脊梁山脈・石鎚山系に属する、愛媛で6番目に高いお山です。。
石鎚国定公園。
昭和30年(1955)に指定。
西黒森は「普通地域」に属します。
西日本最高峰・石鎚山を頂点に東西約50kmに及ぶ石鎚山脈の東翼に位置します。
1500~1900m弱級の山山がいくつも連なる雄峰のひとつです。
瓶ヶ森のすぐ東隣に座し、標高は瓶ヶ森に30m及ばないものの、1861m。
西黒森以東、1800mを越えるお山は、笹ヶ峰(1860m)までありません。
愛媛と高知の県境に位置する山並みは、瀬戸内海と太平洋の分水嶺です。
北斜面に降った雨水は、西条の加茂川になります。
南斜面は、「四国三郎」吉野川の源流域です。
麓の白猪谷から徳島県徳島市の河口まで、全長194kmにおよぶ一級河川の源があります。
西の登山口に「吉野川源流碑」があります。
東の登山口側にある神鳴池は、吉野川の源流と昔から云われてきました。
古くは「おも池」と呼ばれ、雨乞いにまつわる伝説があります。
西黒森周辺は地層的には、中央構造線の外帯に接する三波川変成帯です。
三波川結晶片岩を基盤岩とし、「伊予の青石」の名でも知られる緑色片岩が主です。
中生代前期白亜紀から新生代古第三紀にかけて形成されました。
1500万年前、石鎚山は円錐形の富士山のような姿をした火山でした。
第三紀(2303万年前~260万年前)の末頃、周辺で隆起が始まりました。
石鎚山脈として急激に隆起し始めたのは、第四紀(約260万年前~現代)です。
大断層「中央構造線」の活動により、いまだに隆起し続けています。
日当たりのいい南斜面を中心に、瓶ヶ森林道付近など、ササに覆われています。
山頂付近などにもササ原が点在しています。
全体的には、カエデやブナのほか、モミなどの針葉樹が山肌を覆っています。
黒々と生い茂る濃い樹層の森のイメージから、一帯が黒森と総称されていました。
後に、西にあるピークを西黒森、東にあるピークを東黒森と区別されるようになりました。
霊山の側面がある石鎚山や瓶ヶ森と異なり、西黒森に訪れる人は近代になってからです。
瓶ヶ森林道が開通するまでは、山仕事や狩猟で訪れる人のみの世界でした。
現在のような縦走路もありませんでした。
西黒森が登山目的で縦走された最も古い記録は、大正12年(1923)7月です。
相原正一郎、岡本重彦、篠原要、長岡米吉の4名。
石鎚山から筒上山、瓶ヶ森を経て伊予富士に至っています。
※大正10年7月、松山高等学校旅行部13名による、堂ヶ森~三森峠の縦走記録があります。
けれど、雨により、寺川に下り、子持権現から伊予富士間は通過しませんでした。
昭和4年(1929)7月には、松岡貞蔵と杉浦清両が、瓶ヶ森~笹ヶ峰間を完全縦走しています。
積雪期の縦走は、昭和11年(1936)12月。
谷野芳輝・平田勉・松本園次郎が、笹ヶ峰から瓶ヶ森、石鎚山、堂ヶ森に至った記録があります。
西黒森山頂を通過したかは定かではありませんが。
現在の縦走路は、行政や登山関係者らにより登山道整備されたものです。
現在は瓶ヶ森林道で簡単にアクセスすることができます。
瓶ヶ森林道は昭和43年、瓶ヶ森の氷見二千石原を横断するルートで計画されました。
けれど、山岳連盟などから批判を受け、現在のルートに変更。
土小屋~瓶ヶ森間、全長15.5kmの林道が貫通したのは、昭和46年(1971)10月でした。
(※有料道路として一般供用開始されたのは、翌年からです。)
石鎚スカイラインの開通は、前年の昭和45年(1970)9月。です。
さらに、瓶ヶ森~寒風山隧道間の林道工事が完工したのは、昭和49年(1974)3月でした。
ここでようやく、西黒森までクルマでアクセスすることが可能となりました。
(但し、しばらくは営林局・営林署の事業専用道路でした。)
2020年11月、遭難死亡事故がありました。
広島県から来られた女性が下山中、滑落し、亡くなられました。
背の高いササで道が見えにくい場所もあります。
くれぐれもご注意下さい。
|